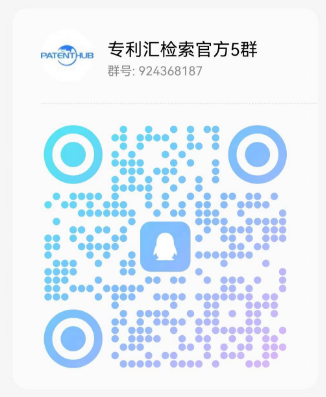Artificial milk and systems for breast-feeding in infants |
|||||||
| 申请号 | JP2006502258 | 申请日 | 2004-02-09 | 公开(公告)号 | JP2006517105A | 公开(公告)日 | 2006-07-20 |
| 申请人 | ユニバーシティ カレッジ ロンドンUniversity College London; | 发明人 | シンハル,アトゥール; ルーカス,アラン; | ||||
| 摘要 | 生後2週間の間に乳児に授乳するための乳児用人工乳であって、長期的な健康に有益であり、人工乳100mlあたり0.5から1.00グラムの蛋白質と、人工乳100mlあたり25から50キロカロリーのエネルギーを含む。 また、複数の区画(たとえば14の区画)を含む容器で、乳児に1日に与える所要量が各容器に入っているような容器。 | ||||||
| 权利要求 | 100mlあたり0.5から1.00グラムの蛋白質と、100mlあたり25から50キロカロリーとを含む、乳児に授乳するための人工乳。 前記蛋白質が、 牛乳カゼイン、乳清蛋白、およびそれらの個々の蛋白質、αカゼイン、βカゼイン、κカゼイン、αラクトアルブミン、βラクトグロブリン、血清アルブミン、ラクトフェリン、免疫グロブリン、およびこれらの蛋白質の組み合わせ、ならびにこれらと他の蛋白質との混合物 の中から選択されることを特徴とする、請求項1に記載の乳児に授乳するための人工乳。 エネルギーが炭水化物および/または脂質の形であることを特徴とする、請求項1または2に記載の乳児に授乳するための人工乳。 水と、請求項1から3のいずれか一項に記載の授乳するための人工乳とを含むことを特徴とする、乳児に授乳するための液体人工乳。 栄養人工乳を含む複数の区画を有する容器であって、 各区画は、請求項1から4のいずれか一項に記載の乳児に授乳するための人工乳を含むことを特徴とする容器。 各区画が、1日あたり10から1200ml、またはその分割された一部を含むことを特徴とする、請求項5に記載の容器。 各区画が、1日あたり10から650ml、またはその分割された一部を含むことを特徴とする、請求項5に記載の容器。 前記分割された一部が、 8分の1ずつ8個に、6分の1ずつ6個に、4分の1ずつ4個に、3分の1ずつ3個に、または2分の1ずつ2個に 分割されていることを特徴とする、請求項6または7に記載の容器。 前記人工乳を含む複数の小袋を各容器が含むことを特徴とする、請求項5から8のいずれか1項に記載の容器。 14個の区画があることを特徴とする、請求項5から9のいずれか1項に記載の容器。 栄養人工乳を含む複数の区画を有する容器であって、 各区画は、乳児の1日の摂取量として十分な栄養人工乳を含むことを特徴とする容器。 前記人工乳が、標準的な乳児用人工乳を含むことを特徴とする、請求項11に記載の容器。 各区画が、1日あたり10から1200ml、またはその分割された一部を含むことを特徴とする、請求項11または12に記載の容器。 各区画が、1日あたり10から650ml、またはその分割された一部を含むことを特徴とする、請求項11または12に記載の容器。 前記分割された一部が、 8分の1ずつ8個に、6分の1ずつ6個に、4分の1ずつ4個に、3分の1ずつ3個に、または2分の1ずつ2個に 分割されていることを特徴とする、 請求項11から14のいずれか1項に記載の容器。 前記人工乳を含む複数の小袋を各容器が含むことを特徴とする、請求項11から15のいずれか1項に記載の容器。 14個の区画があることを特徴とする、請求項11から16のいずれか1項に記載の容器。 |
||||||
| 说明书全文 | 本発明は、栄養物、および乳児に授乳するための授乳システムに関し、より詳細には、そのうち生後最初の数週間以内の乳児用のものに関する。 ベビーフード、特にミルクベビーフードや乳児用人工乳を作るには、それぞれ、とりわけ牛乳や牛乳から得られる成分が使われる。 これらは、たとえば、牛乳蛋白質(カゼインや乳清蛋白)を含む。 牛乳と人間の母乳には多くの相違点がある。 現代の商用の乳児用人工乳を製造する過程では、人工乳食物でも同様なのだが、牛乳を非常に大きく変える必要がある。 そのような人工乳食物は、できるだけ母乳を「そのとおりに」模倣することを意図して、「人工的に」製造される。 また、そのような人工乳食物は、動物性および/または植物性の出発原料から製造されるが、これら出発原料は、特に蛋白質、脂質、炭水化物である。 生後最初の数週間がもっとも成長が速い。 そして現在の公衆衛生の勧告と実務は、人間の幼児の成長の推進を強く支持しており、乳児の成長を促すために、生後数週間以内の乳児に与えるための乳児用人工乳が考案されてきた。 栄養不足の期間を補償するために、好ましい条件下で成長を加速する能力は、多くの発展途上の有機体に共通の戦略であり、栄養不足の幼児や子供の栄養上のリハビリテーションの基礎である。 しかし健康な新生児に関しては、我々の研究から次のことが分かった。 初期の速い成長または「過栄養」によって、人間の場合は、長期的には不利な健康上の効果が見られる。 特に、アテローム性動脈硬化の発達や、後になって現れるインスリン抵抗性糖尿病やインスリン非依存性糖尿病(NIDDM)の傾向に関連がある、長期的な血管の健康に関して、長期的には不利な健康上の効果が見られる。 後年のインスリン抵抗性をより低くすることを計画した栄養摂取の抑制で証明されたとおり、比較的栄養不足であることの結果として、よりゆっくり成長することは、良い効果があると示唆されてきた。 我々は次のことも発見した。 人工乳を与えられた乳児は、母乳を与えられた乳児よりも、最初の2週間の体重増加量が大きい。 そして、心臓血管の健康に関して、母乳を与えた方が長期的に良い効果が示唆されているということは、この決定的な早期の期間中、母乳を与えられた乳児の栄養摂取量がより小さいことの結果なのかもしれない。 成長の加速のほとんどは生後2ヶ月までに完了するので、母乳を与えることで栄養摂取量がより低くなることによる、血管の健康に関する長期的な利点は、この期間に起こる傾向がある。 成長率に影響する、乳児用人工乳の主要な構成要素は、人工乳の蛋白質含有量とエネルギー含有量である。 乳児に与えるための人工乳として提案されているものや既存のものよりも低い栄養摂取量となる人工乳を、我々は考案した。 100mlあたり0.5から1.0グラムの蛋白質を含み、100mlあたり25から50キロカロリーのエネルギーを含む、乳児に与えるための人工乳が、本発明によって示される。 蛋白質とエネルギーのこれらの水準は、乳児に与えるための人工乳として提案されてきたものよりも下である。 そして、そのような構成は新規であり、乳児にとって長期的な健康により良い結果になりうるというのは驚くべきことである。 本発明による人工乳食物(つまり、乳児に与える人工乳またはベビーフード)には、既に現在人工乳食物の製造で使われている通常の蛋白質を、原材料として使うことができる。 つまり、ベビーフード用の蛋白質として使うことができる。 本発明によれば、これまでに公知のすべての蛋白質源、たとえば、蛋白質、オリゴペプチド、ジペプチド、および/または遊離アミノ酸(その塩の形で存在することもありうる)の塩酸塩などが使える。 よって、牛乳カゼイン、乳清蛋白質、およびそれらの個々の蛋白質(αカゼイン、βカゼイン、κカゼイン、αラクトアルブミン、βラクトグロブリン、血清アルブミン、ラクトフェリン、免疫グロブリン)、およびこれらの蛋白質の組み合わせ、さらに他の蛋白質(たとえば大豆蛋白質)との混合物、が使える。 他の動物性または植物性の蛋白質で、人間の栄養に適しているものも、使える。 既存の人工乳で使われ認可されてきたタイプの、脂質、炭水化物、蛋白質の形で、総エネルギーは供給されうる。 本発明の人工乳は、典型的には生後最初の2週間に、乳児に与えられる。 しかし、2ヶ月まで使われてもよい。 2ヶ月という期間は、ほとんどの成長加速が完了する時期である。 我々は、これを確実にするのに役立つ授乳システムも考案した。 各区画で、人工乳の重さは、1日の授乳に必要な量であってもよい。 これは好ましくは、1日あたり10mlから1200mlで、さらに好ましくは10mlから650mlである。 使われる人工乳は、標準的な乳児用人工乳か、好ましくは、100mlあたり0.5から1.0グラムの蛋白質を含み、100mlあたり25から50キロカロリーの上記の低栄養人工乳である。 状況に応じて、1日の所要量の全てを1つの区画に入れるかわりに、1日の所要量を1つより多い区画に分散してもよく、好ましくは、容器は適切に印をつけてあるとよい。 もし乳児に4時間ごとに授乳するなら、各区画が1日の栄養所要量の6分の1を保持できるように、1日の所要量をたとえば、8分の1ずつ8区画に、6分の1ずつ6区画に、4分の1ずつ4区画に、3分の1ずつ3区画に、2分の1ずつ2区画に、分割してもよい。 本発明の人工乳は、典型的には生後最初の2ヶ月までの乳児に与えられる。 その後は、乳児は通常の食物を与えられてもよい。 よって、各容器が2ヶ月までの供給量を保持してもよいし、各容器が2ヶ月の供給量を保持するのに十分な区画を含んでもよい。 あるいは、1つより多い容器があって、たとえば、2週間の供給量を含む容器には14区画というふうに、2ヶ月より短い期間に対応する区画を、設定された数ずつ各容器が含むようにしてもよい。 容器はどのような便利な形でもよい。 また、たとえば、容器がボール紙のシート、プラスチック、またはその類似物を含み、シートに接着されたプラスチック製の球状部品(bubble)によって区画が作られていてもよい。 あるいは、容器は、区画を形成する人工乳の小袋を含む、缶や箱、またはその類似物でもよい。 乳児が栄養不良または栄養過多にならないようにするために、また、人工乳を簡単かつ便利に保存し利用するために、乳児が授乳されるべきときには、1日ごとに乳児にどれだけの量の人工乳を与えるべきか、授乳者が正確に知るようにするのは簡単である。 長期の健康に対する早期の低栄養の影響が、人口母集団内の制御された比較群で測定された。 また、その結果が下記の例に示されている。 例1 並行2群間無作為化試験(two parallel randomized trials)によって、早産児は出生時に異なる規定食に無作為に割り当てられる。 これらの試験では、栄養豊富な早産児用人工乳(英国アクスブリッジのストックリー・パークにある、HJハインツ社の部門Farley's Health CareのFarley's Osterprem)と、その時点で利用可能な相対的に低い栄養の規定食とを比較した。 試験1では、早産児用人工乳と、授乳中の無関係な女性から提供された保存母乳を比較した。 そして試験2では、同じ早産児用人工乳と、標準的な正期産児用人工乳(Farley's Ostermilk)とを比較した。 各試験(1と2)内で、規定食は無作為に2つの層(A:規定食のみの試験、B:選ばれて母乳を出す母親がいる)に割り当てられた。 試験の規定食は、母乳への栄養補助食品として割り当てられた(表1を参照)。 栄養豊富な早産児用人工乳と、より低い栄養の規定食を比較するために、もともと計画されていたとおり、試験1と2(そして各試験内の層AとB)が、均衡した数(balanced addition)として組み合わされて、それにより、無作為化が維持された。 規定食への無作為な割り当ては、生後48時間以内に封をした封筒を使って行われた。 試験に対する倫理的な承認が各センターから得られた。 また、それぞれの親からインフォームドコンセントが得られた(同意を拒否した親はいない)。 割り当てられた規定食は、乳児が2000gになるか、退院して家に戻るまで、与えられた。 正期産児用人工乳と比べて、早産児用人工乳は蛋白質と脂質に富んでいた(早産児用人工乳は100mlあたり2.0gの蛋白質と4.9gの脂質だが、正期産児用人工乳は100mlあたり1.5gの蛋白質と3.8gの脂質である)。 しかし、炭水化物はどちらの人工乳でも同じ(7.0g/100ml)である。 早産児用人工乳は、ビタミン、亜鉛、銅にも富んでいた。 提供された保存乳を与えられる乳児に対しては、蛋白質とエネルギーの摂取量は、複数の提供者から集められた、600の貯蔵された提供母乳から見積もられた(100mlあたりおよそ1.1gの蛋白質、2gの脂質、7gの炭水化物)。 母親自身が出す母乳の構成は、完全24時間制で4935回採集されたものから計測された(およそ1.5gの蛋白質、3gの脂質、7gの炭水化物)。 広範囲の人工統計学的、社会的、人体計測的、生化学的、臨床的なデータが、病院の承認を通じて集められた。 訓練をつんだスタッフが、毎日乳児の体重を測定した。 そして、体重の日々の揺れに起因する誤りを減らすために、生後各週の平均体重が計算された。 新生児部門から退院した後も、18ヶ月、9〜12歳、および13〜16歳の時点の体重が利用可能だった。 社会階級は、戸籍本署長官の分類(Registrar Generals Classification)での記述にしたがい、家族に対する主要な財政的支持を与えている親の職業(または、両親とも働いている場合は父親の職業)に基づいた。 追跡調査 FMD測定 追跡調査における人体測定及び生化学 前夜から食事を断った後の午前9時から11時の間に、静脈穿刺によって血液を採取した。 血漿がすぐに分離され、最初は−20℃で、やがては−80℃で保管され、分析の直前に1回だけ解凍された。 LDLコレステロールの血漿中の濃度が、標準的な検査室手法によって計測された。 統計学的な分析 結果 妊娠期間別の出生時体重および後のFMD 妊娠期間別の出生時体重および生後早期の成長 生後の成長と後のFMD 後のFMDに影響する、新生児期の成長の期間をより良く定義するために、出生と退院の間の期間が2つに分割された(出生と第2週の間、第2週と退院の間)。 出生と第2週の間は成長率がより大きいが、第2週と退院の間はそうではない、ということが、青年期のより低いFMDと関連していた。 そしてこの関連性は、潜在的な交絡因子(上記のとおり)に対して調整した後でもまだ有意だった(表2)。 同様に、生後最初の2週間で体重増加がより大きいことが、青年期のより低いFMDと関連していて(表1a)、出生時体重、妊娠期間、および考えられる交絡因子(上記のとおり)とは独立だった(表2)。 生後の体重増加よりも体液移動による生後の体重減少が後のFMDに影響したという可能性を排除するため、さらに2つの分析が行われた。 第1に、生後最小の体重と第2週時点の体重との間の体重増加と、後のFMDとの関連を評価した。 この期間中により大きく体重が増加することは、青年期のより低いFMDと関連しており、出生時体重、妊娠期間、および潜在的な交絡因子(上記を参照)とは独立だった(表2)。 第2に、出生時と第2週時点の間の身長の増加(生後の体液移動とは関連しそうにない)が、青年期のより低いFMDと関連しており、出生時体重、妊娠期間、および潜在的な交絡因子とは独立だった(表2)。 生後早期の成長と後のFMD:群の比較 後のFMDに対する、子宮内と生後早期の成長の相対的寄与率 生後最初の2週間の決定的な期間中、体重増加率がより大きいことは、後の16年までの内皮機能不全に関連していた。 我々のデータが示しているのは、人間の場合、生後すぐに急激に成長することは、後の人生で不都合な結果になるということである。 より遅い成長率の早産児におけるFMDは、最大の成長を示した早産児におけるFMDよりも大きく、あるいは、重要なことに、正期産で生まれた対照被験者におけるFMDよりも大きかった(これら後者2群におけるFMDは、有意な差がない)。 よって、ここで我々の所見から示されることは、生後の短い期間中の成長の減少が、健康にとって長期的な利点となるかもしれないということである。 我々のデータが示しているのは、早期の低栄養によって、長期的な健康のいくつかの面における改善が達成されうるということである。 生後最初の2週間は、感受期であるようだ。 この期間中に最大の体重増加が見られた青年は、最小の体重増加だった者に比べて4.0%低いFMDだった。 FMDに対する実質的な影響は、インスリン依存性糖尿病による影響(4%)や、成人の喫煙による影響(6%)と同程度である。 例2 インスリン抵抗性に対する低栄養の影響 各試験において、無作為化された規定食群間の結果における2分の1標準偏差の差を除外するように、標本サイズが見積もられた。 我々は、80%の検出力、5%の有意性で(2つの並行な試験に関して)この違いを検出するために、元のコホートから、約250名の被験者からなる最大の副標本を必要とした。 70%の検出力、5%の有意性に対しては、約200名の被験者からなる最小の標本が必要だった。 216名からなる被験者の部分集合(我々の最小限の基準を満たす)が、募集時の我々の最初の計画に参加することに同意し、もとの母集団の代表者であると認められた。 栄養豊富な規定食と標準的な新生児用規定食とを比較するため(試験1と2が結合された)、この標本は、80%の検出力、5%の有意性で、無作為化された群間の空腹時32―33分割プロインスリン濃度における0.4SD(標準偏差)の差を検知するのに十分だった。 追跡調査のための倫理的承認が、国および地域の研究倫理委員会から得られ、全ての子供、親および保護者から、書面での同意が得られた。 生化学 統計学的な分析 重回帰分析を使って、新生児期および児童期の成長(体重増加)率と、後のインスリン濃度との間の関連性を評価した。 新生児期の体重増加は、絶対値として表され、また、早産児用の百分位数を使って、体重の期待値からの標準偏差スコア(zスコア)として表された。 新生児期より後の成長は、退院時と18ヶ月時点の間、18ヶ月時点と9〜12歳時点の間、9〜12歳時点と13〜16歳時点の間での、体重のzスコアの変化として計算された。 現在のボディ・マス・インデックス(BMI)は、国民参照百分位数(national reference centile)を用いて、BMIの期待値からの標準偏差スコア(zスコア)として表された。 32―33分割プロインスリン、プロインスリン、およびインスリンの濃度の分布は、対数変換されて、100倍された。 よって、100倍された対数標準偏差は変動の係数を表し、回帰分析における係数は、独立変数における単位変更による(per unit change)インスリン濃度の平均百分率変化を表した。 回帰分析は潜在的な交絡因子(性別、年齢、現在の追跡調査時におけるBMIのzスコア、および新生児罹病率(30%より高い酸素濃度の中にいた日数、換気日数)、出生時の社会階級)に対して調整された。 統計的な有意性は、全ての有意性検定でp<0.05とされ、検定は両側検定で行われた。 結果 主要な効果:無作為化された規定食群間の比較 典型的な分析では、32―33分割プロインスリン濃度に対する規定食の効果は、出生時体重と妊娠期間、および潜在的な交絡因子に対して調整した後(上記の統計手法を参照)もまだ有意だった(回帰係数=18.4%;差の95%信頼区間は3.5%から33.2%;p=0.016)。 32―33分割プロインスリンとインタクト・プロインスリンの濃度に対するその後の分析(インスリンまたはグルコースの濃度は分析対象外)では、早期の利益の因子(early factors of interest)に有意に関連していた(他のデータは示さない)。 生後早期の成長計画の、後のプロインスリン濃度に対する影響 新生児期のより大きな成長率(連続変数、つまり、出生時と退院時の間の体重のzスコアの変化として表される)は、青年期における、より高い空腹時の32―33分割プロインスリンおよびインタクト・プロインスリンと関連しており、出生時体重、妊娠期間、および潜在的な交絡因子(上記の統計手法を参照)とは独立だった(表5)。 後のプロインスリン濃度に影響する新生児期の成長の期間をより良く定義するために、出生と退院の間の期間が2分割された(出生と第2週の間と、第2週と退院の間)。 最初の2週間の成長のみが、青年期における、より高い空腹時の32―33分割プロインスリンおよびインタクト・プロインスリンの濃度と関連していた(表5)。 生後最初の2週間に体重が増加した被験者(n=60)と体重が減少した被験者とを比較することにより、新生児期の成長が2値変数として扱われた。 空腹時の32―33分割プロインスリン濃度は、新生児早期の体重増加があった被験者の方(幾何平均7.6pmol/L、変動係数(CV)60%)が、体重減少があった被験者(5.9pmol/L、CV54%)に比べて、高かった(平均差24%;差に対する95%信頼区間は6.6%から41.5%;p=0.007)。 インタクト・プロインスリンに対しても同様の結果が得られた(p=0.0003)(データは示していない)。 新生児期の体重増加に関する群間での、32―33分割プロインスリンまたはインタクト・インスリンの濃度の違いは、出生時体重や妊娠期間に対して調整した後もまだ有意だった(32―33分割プロインスリンについてはp=0.02でインタクト・プロインスリンについてはp=0.03)。 生後の体重増加よりも、体液移動による生後の体重減少が、後の空腹時インスリン濃度に影響したという可能性を排除するため、我々は、生後最小の体重と第2週時点の体重との間の体重増加と、後のプロインスリン濃度との関連を評価した。 この期間中により大きく体重が増加することは、青年期のより高い32―33分割プロインスリン濃度およびインタクト・プロインスリン濃度と関連しており、出生時体重、妊娠期間、および潜在的な交絡因子(上記を参照)とは独立だった(表5)。 後のプロインスリン濃度に対する、新生児期より後の生後の成長の影響を評価するために、成長は、退院時と18ヶ月時点の間、18ヶ月時点と9〜12歳時点の間、または9〜12歳時点と13〜16歳時点の間における、体重のzスコアの変化として表された。 これらの変数は、後の32―33分割プロインスリンまたはインタクト・インスリンの濃度と有意に関係してはいなかった。 さらに、生後最初の2週間でのより急激な成長は、青年期における、より大きな32―33分割プロインスリン濃度と関連しており、現在のBMIのzスコアに対する調整の有無によらず、関連していた(データは示していない)。 よって、後の32―33分割プロインスリン濃度に対する早期成長の影響は、児童期の間の体重増加とは独立だった。 出生前の成長計画のプロインスリン濃度に対する影響 将来に向けた我々の実証研究は、後の心臓血管の危険因子に対する、早期の栄養の影響を評価するように設計された。 早産で生まれてより低栄養の規定食に無作為に割り当てられた青年は、今や、成長の観点からは次善であると認識され、インスリン抵抗性の標識である32―33分割プロインスリン濃度が、栄養豊富な規定食に無作為に割り当てられた青年よりも低いことが分かった。 食事に関する無作為化の後16歳までに見られるこれらの食事の影響は、新生児期の成長率に影響を与えることによって作用するようだ、ということが、さらに進んだ分析によって示唆された。 よって我々は、比較的低栄養の計画の結果として、早期の成長率を減らすこと、インスリン抵抗性がより低くなることを示唆し、推論によって、NIDDMの傾向がより低くなることを示唆する。 |
||||||