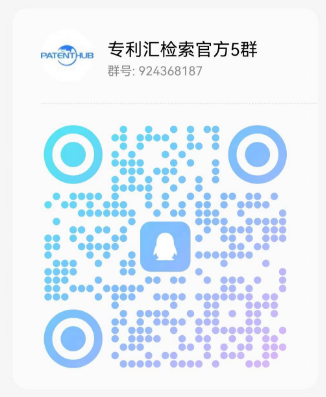Antenna element |
|||||||
| 申请号 | JP2008015680 | 申请日 | 2008-01-25 | 公开(公告)号 | JP4977048B2 | 公开(公告)日 | 2012-07-18 |
| 申请人 | キヤノン株式会社; | 发明人 | 健明 井辻; | ||||
| 摘要 | |||||||
| 权利要求 | 所定の周波数帯域で動作するアンテナ素子であり、 共振部と、半導体部と、アンテナ部とを有し、 前記共振部は、第1導体部と、誘電体部と、前記誘電体部を介して前記第1導体部と対向して配置される当該アンテナ素子の各部に対して基準の電位を規定するための第2導体部とを含み、 前記半導体部は、前記第1導体部と前記第2導体部に挟まれて配置されており、 前記アンテナ部は、前記第2導体部を接地導体とし、立体状且つ少なくとも表面が導電性であり、前記第1導体部上に配置される、 ことを特徴とするアンテナ素子。 前記第1導体部は、前記所定の周波数帯域内の電磁波の実効的な最長波長をλとして、λ/2の長さを有する、 ことを特徴とする請求項1に記載のアンテナ素子。 前記アンテナ部は、前記所定の周波数帯域内の電磁波の電磁界の節となる位置に配置される、 ことを特徴とする請求項1または2に記載のアンテナ素子。 前記第1導体部上の前記アンテナ部の配置位置は、前記所定の周波数帯域内の電磁波の電磁界の節となる位置からずらすことによって当該アンテナ素子内を伝播する電磁波の位相状態を変化させられる様に、可変である、 ことを特徴とする請求項1または2に記載のアンテナ素子。 前記アンテナ部は、前記所定の周波数帯域内の電磁波の実効的な最長波長をλとして、λ/4からλの長さを有する、 ことを特徴とする請求項1から4のいずれかに記載のアンテナ素子。 前記アンテナ部を前記第1導体部上に保持する保持部を更に有している、 ことを特徴とする請求項1から5のいずれかに記載のアンテナ素子。 前記保持部は、当該アンテナ素子を伝播する電磁波の伝播方向における前記アンテナ部の配置位置を可変とできる様に前記第1導体部の長手方向に移動可能である、 ことを特徴とする請求項6に記載のアンテナ素子。 前記半導体部は、前記所定の周波数帯域内の電磁波に対し、利得を有している、 ことを特徴とする請求項1から7のいずれかに記載のアンテナ素子。 前記半導体部は、光照射により伝導性を示す光伝導膜である、 ことを特徴とする請求項1から7のいずれかに記載のアンテナ素子。 前記所定の周波数帯域は、30GHzから30THzの範囲内にある、 ことを特徴とする請求項1から9のいずれかに記載のアンテナ素子。 テラヘルツ波発振素子であって、 波長λのテラヘルツ波に対する利得を有する利得部と、 前記利得部と接する誘電体と、 前記誘電体と接し、且つ略λ/2の長さの線路形状を有する第1の導体部と、 前記誘電体と接し、前記誘電体を介して前記第1の導体部と対向して配置され、且つ平板形状を有する第2の導体部と、 前記第1の導体部と接し、且つ導体を含み構成される高さ略λ/4以上略λ以下の構造物と、を備え、 前記誘電体と前記第1の導体部と前記第2の導体部とにより構成されるマイクロストリップラインは、前記利得部で発生されたテラヘルツ波を伝播させるように構成され、 前記構造物は、発振における位相条件を満たす前記第1の導体部の位置に設けられる、 ことを特徴とするテラヘルツ波発振素子。 前記構造物の前記第1の導体部における前記利得部からの距離が、該構造物のインピーダンスに応じて調整されることにより、前記発振における位相条件が満たされる、 ことを特徴とする請求項11に記載のテラヘルツ波発振素子。 前記構造物は、誘電体から成る球と、該球の表面を覆う金属とから構成され、 前記距離は、前記誘電体の面内方向に略λ/4である、 ことを特徴とする請求項12に記載のテラヘルツ波発振素子。 前記利得部は、共鳴トンネルダイオードであり、 前記構造物は、シリコン球と、該シリコン球の表面を覆う金属とから構成され、 前記距離は、前記誘電体の面内方向に略λ/4である、 ことを特徴とする請求項12に記載のテラヘルツ波発振素子。 前記マイクロストリップラインは、該マイクロストリップラインの両端で反射された前記テラヘルツ波を共振させるように構成される、 ことを特徴とする請求項11に記載のテラヘルツ波発振素子。 請求項11に記載のテラヘルツ波発振素子を設置可能に構成される装置であって、 前記第1の導体部と前記第2の導体部とに電圧を印加するためのバイアス回路を備え、 前記バイアス回路の前記利得部からの距離は、前記誘電体の面内方向に略λ/4である、 ことを特徴とする装置。 |
||||||
| 说明书全文 | 本発明は、アンテナ部と電磁波発生ないし検出媒質を集積化したアンテナ素子に関するものである。 より詳しくは、30GHzから30THzのうちの任意の帯域を有する高周波電磁波(本明細書ではテラヘルツ波と呼ぶ)を発生ないし検出するアンテナ素子に関する。 近年、テラヘルツ波を用いた非破壊な検査技術が開発されている。 テラヘルツ波の周波数領域には、生体分子をはじめとして、様々な物質の吸収線が存在することが知られている。 この周波数領域の応用分野として、X線に替わる安全な透視検査を行うイメージング技術がある。 また、物質内部の吸収スペクトルや複素誘電率を求めて、分子の結合状態を調べる分光技術がある。 また、生体分子の解析技術、キャリヤ濃度や移動度を評価する技術等が期待される。 これらの技術開発において、テラヘルツ波の発生、検出技術は重要である。 こうした技術として、半導体基板上に、平面型のアンテナパターンと微小な空隙をパターニングし、テラヘルツ波の発生、検出素子とする技術がある(非特許文献1参照)。 この素子は、超短パルスレーザによって空隙にキャリヤを励起させ、別途空隙に印加された電界によってキャリヤを加速させることでテラヘルツ波を得るものである。 この素子構成は、検出素子としても適用できる。 また、テラヘルツ波を発生させる手法として、半導体技術を用いたものがある。 例えば、ガンダイオードや共鳴トンネルダイオード(RTD)等の利得媒質を用いたものがある。 これらの利得媒質を発生器として用いる場合、これらの利得媒質を含んだ発振回路を構成し、所望の周波数領域について適当に負荷抵抗と位相を調整することで、発振状態を実現する。 従来、この様にして得られた電磁波は、アンテナ等の放射素子に接続され、外部に放射されることが多い。 ところが、高周波領域になると、電磁波の伝播ロスや、個別に設計された素子間のミスマッチによって、効率良く電磁波を外部に放射することが難しくなる。 そこで、このアンテナ素子も発振回路を構成する負荷抵抗の一部とみなし、一体的に設計、集積化を行う試みがなされている(非特許文献2参照)。 非特許文献2は、伝送線路(マイクロストリップライン(MSL))型のアンテナ発振器である。 このアンテナ発振器は、伝送線路を構成する誘電体の膜厚方向に形成されたガンダイオードに対し、パッチアンテナを接続している。 このアンテナ発振器は、下の式(1)と(2)に示した発振開始条件を満たすため、パッチアンテナを負荷抵抗の一部として用いる。 そして、位相条件を満たすために、位相調整用のスタブを用いている。 また、パッチアンテナと他の伝送線路で構成される回路は、インピーダンス変換回路によって接続されている。 全体として、本アンテナ発振器は、平面状に集積される構成となる。 アドミッタンスの実部:Re[Y act +Y load ]<0 (1) 尚、利得と位相の条件を夫々示す式(1)と(2)において、Y actとY loadは、利得素子(ガンダイオード)のアドミッタンスとアンテナを含む伝送線路型の発振回路のアドミッタンスに、夫々対応している。 非特許文献1で示した様な光伝導素子によって発生するテラヘルツ波の帯域は、半導体のキャリヤの移動度によって規定される。 一般的に、この様な半導体基板は、誘電率が高い。 そのため、半導体基板と大気の境界における屈折率差によって、テラヘルツ波の一部が全反射し、半導体基板内に閉じ込められてしまう。 よって、テラヘルツ波の取り出し効率が劣化する。 この様な界面における反射条件を緩和し、テラヘルツ波を外部に取り出すため、例えば、半導体基板と同等な材質によって、半球レンズを基板側に取り付けるという手法がある。 ただし、この場合は、半球レンズと基板間の隙間に介在する空気層による反射の影響や、半球レンズにおける伝播損失によって、取り出し効率が劣化する。 また、非特許文献2で示した技術は、利得媒質に対し、アンテナを含む発振回路を並列に接続し、発振器として機能させている。 一般的に、高周波回路では、波長が短くなるに伴い、回路規模が小さくなる。 その結果、負荷抵抗の一部として用いたアンテナ素子に、十分な負荷抵抗を与えることが困難になる。 より詳しくは、波長が短くなるに伴い、アンテナ素子の抵抗値が低下する。 アンテナ素子は、利得媒質に対して並列に接続されているため、アンテナ素子の抵抗値の低下に伴い、Y loadの値が大きくなる。 その結果、テラヘルツ波領域において、上記アドミッタンスの実部の条件(1)を満たすことが難しくなり、発振器としての動作が不安定になりやすい。 また、波長によっては、発振させること自体が難しくなるという課題がある。 上記課題に鑑み、本発明の所定の周波数帯域で動作するアンテナ素子は、共振部と、半導体部と、アンテナ部とを有する。 前記共振部は、第1導体部と、誘電体部と、前記誘電体部を介して前記第1導体部と対向して配置される当該アンテナ素子の各部に対して基準の電位を規定するための第2導体部とを含む。 前記半導体部は、前記第1導体部と前記第2導体部に挟まれて配置されている。 前記アンテナ部は、前記第2導体部を接地導体とし、ほぼ立体状且つ少なくとも表面が導電性であり、前記第1導体部上に配置される。 前記所定の周波数帯域は、例えば、30GHzから30THzの範囲内にある。 本発明におけるアンテナ素子は、アンテナ部が外部(共振部の第1導体部上)に支持される構成である。 そのため、平面アンテナ構造に比べ、誘電体部による損失を低減できる。 よって、電磁波の取り出し効率(検出では取り込み効率)が向上するという効果がある。 以下に、本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。 尚、図中、同一機能の要素に関しては、同符号を用いる。 図1は、本発明におけるアンテナ素子の一実施形態の概略構成図である。 図1の様に、本実施形態のアンテナ素子は、第1導体部101、アンテナ部102、第2導体部103、誘電体部104、半導体部105で構成される。 尚、図1の様に、第2導体部103に対し、面方向をXY方向、法線方向をZ方向と定義する。 図2は、図1におけるアンテナ素子の断面図を示したものである。 (a)は、第1導体部101の長手方向に沿ったYZ面での断面図である。 (b)は、アンテナ部102の中心部分におけるXZ面での断面図である。 以後の説明は、図1と図2の両方を対比させて行う。 第1導体部101は、導電性の細長い線路である。 線路長をL、線路幅をw、線路高さをtと定義する。 第1導体部101には、好適には、金属導体が用いられる。 誘電体部104を介して第1導体部101と対向して配置される第2導体部103は、平板状の導体である。 この導体の高さをtと定義する。 ここでは、第1導体部101と第2導体部103の高さは、便宜上同じとしているが、異なっていてもよい。 第2導体部103は、アンテナ素子の各部に対して基準の電位を規定している。 これも、好適には、金属導体で構成されるが、半導体基板にキャリヤをドープして導電性を持たせた構成でもよい。 誘電体部104は、第2導体部103界面に積層される誘電体薄膜である。 この誘電体薄膜の厚みをdとする。 誘電体部104の厚みdは、誘電体内への電磁波の閉じ込め効果が起きない程度に、使用する電磁波の波長に対し十分薄く積層する。 使用する誘電体材料としては、使用する電磁波の波長帯において損失が少ないものが望ましい。 例えば、BCB(ベンゾシクロブテン)がある。 ただし、これに限らず、ポリイミド系、ポリオレフィン系の様な樹脂材料を用いてもよい。 また、高抵抗シリコンの様な半導体材料や、メンブレンフィルターに用いられる様な多孔質繊維材料を用いることも可能である。 図1の様に、第1導体部101、第2導体部103、誘電体部104は、マイクロストリップラインと呼ばれる導波路を構成している。 特に、本実施形態では、第1導体部101は、有限の長さLを有している。 このことにより、導波路を伝播する電磁波は第1導体部101の両端面で反射し、共振回路が形成される。 具体的には、導波路を伝播する電磁波の実効的な波長をλとすると、第1導体部101の長さLを1/2・λとすることで、波長λに対する共振回路が形成される。 本明細書では、第1導体部101、第2導体部103、誘電体部104で構成される様な共振回路を共振部と呼ぶ。 尚、実効的な波長λに関し、使用する電磁波が或る任意の周波数帯域を占有する場合、波長λは、アンテナ素子を伝播する上記周波数帯域内の電磁波の実効的な波長における最長波長λを指すこととする。 アンテナ素子のカットオフ周波数の観点から見て、最長波長λにおいて規定すれば、それより短い波長でも、この規定により目論まれる目的が実質的に達せられるからである。 アンテナ部102は、アンテナ部102の表面を電磁波が伝搬するという目的を達成できる立体状の構造物である。 このような構造物として、少なくとも表面が導体であるほぼ球状の構造物がある。 また、構造の一部に錐形状を有する構造物がある。 ほぼ球状の構造物として、完全な球形状や、その一部が球形状から多少変形した非球面形状を有するもの、また、楕円形状などが考えられる。 このような構造物として、例えば、シリコン球の表面を金属でコーティングしたものが使用できる。 ただし、これに限らず、金属自体の球を用いることも可能である。 構造の一部に錐形状を有する構造物として、円錐形状や四角錐形状など各種錐形状が適用できる。 図9は、アンテナ部902として四角錐を適用した例を示している。 また、構造の一部に錐形状を有していればよいので、球形状の一部に円錐形状を組み合わせた構造等が適用できる。 図9のように、アンテナ部902の錐形状の頂点は、第1導体部101に向かっている構造である。 図9の構造は、例えば、錐形状にエッチングした表面に導体を形成するシリコン基板が適用できる。 この場合、誘電体部104に対し、このシリコン基板を張り合わせる構造となる。 また、既知のMEMS(Micro-Electro-Mechanical-Systems)を用いて、錐形状を有する構造体を作製してもよい。 尚、以後の説明では、主としてアンテナ部は、図1に示した完全な球形状のアンテナ部102として説明する。 アンテナ部102は、第2導体部103を接地導体とすることでアンテナとして機能する。 以後、アンテナ部102と第2導体部103を総称して、アンテナ構造と呼ぶ。 このアンテナ構造は、コニカルアンテナの構造に近い。 そのため、周波数特性も、コニカルアンテナと同様に広帯域な特性を示す。 アンテナ部102は、第1導体部101に沿った適当な位置において、第1導体部101上ないしその近傍に配置される。 そして、共振部を伝播する電磁波は、アンテナ構造によって外部に放射される。 アンテナ部102による、共振部を伝播する電磁波への影響を低減するために、アンテナ部102は、ほぼ電磁界の節(電界がほぼ0となる場所)に配置することが望ましい。 ただし、用途によっては、この限りではない。 例えば、共振部とアンテナ構造の配置関係によって位相状態(アンテナ素子内部の位相状態や、放出される電磁波の位相状態)を制御する場合、敢えてアンテナ部102の配置位置を電磁界の節からずらすこともある。 従って、第1導体部上のアンテナ部の配置位置を、上記周波数帯域内の電磁波の電磁界の節となる位置からずらすことによって当該アンテナ素子内を伝播する電磁波の位相状態を変化させられる様に、可変としてもよい。 一般的に、アンテナ部がアンテナとして機能するためには、対象となる波長の電磁波が、アンテナ構造で共振する必要がある。 そのため、アンテナ構造を構成するアンテナ部102の大きさ(その径など)は、上記波長λ程度必要となる。 半導体部105は、誘電体部104内部において、第1導体部101と第2導体部103に挟まれて配置される。 半導体部105の両端部分は、第1導体部101と第2導体部103に対して、夫々接触している。 半導体部105は、キャリヤを発生するまたは利得を有する等、キャリヤを制御する機能を有する部分である。 例えば、外部からの光照射によって伝導性を示す光伝導膜で発生機構を構成する。 共鳴トンネルダイオード(RTD)、量子カスケードレーザ、ガンダイオードなどのように、或る波長に対し利得を有する機構で構成することもできる。 尚、図1のアンテナ素子は、必要に応じ、不図示のバイアス回路を有していてもよい。 バイアス回路は、例えば、第1導体部101と第2導体部103の間(半導体部105の両端)に所定のバイアスを印加するように構築される。 以下に、本アンテナ素子におけるアンテナとしての機能について、解析結果を交えて説明する。 図2の様に、アンテナ部102の配置位置を、第1導体部101の端部からの距離Dとして定義する。 また、第1導体部101とアンテナ部102の界面からのアンテナ高さをHとする。 以後の解析では、D=0の場所に、半導体部105として電磁波源を設置している。 図3は、アンテナ部102の配置位置の距離Dの変化に対する、アンテナ素子の同一周波数(1.2THz)におけるインピーダンスの変化をプロットしたものである。 ここでは、λ=300μm、L=1/2・λ、H=1/3・λ、w=15μm、t=0.5μm、d=3μmとし、簡単化のため、誘電体部104を空気とした。 図3において、D=1/4・λの位置(第1導体部101の中央にアンテナ部102がある)が、電磁界の節に相当する場所であり、Dを変化させることで、位相状態が時計回りに変化している様子が分かる。 例えば、このアンテナ素子を、アンテナ発振回路として用いる場合、Dの位置によって、発振における位相条件を調整することができることを示している。 また、図10は、アンテナ部102を図9に示した錐形状のアンテナ部902に替え、アンテナ部902の配置位置の距離Dの変化に対する、アンテナ素子の同一周波数(1.2THz)におけるインピーダンスの変化をプロットしたものである。 ここで、アンテナ高さHは、第1導体部101からアンテナ部902の底部までの距離としている。 ここで、λ=300μm、L=1/2・λ、H=1/2・λ、w=15μm、t=0.5μm、d=3μmとし、簡単化のため、誘電体部104を空気とした。 また、底部は1辺が200μmの正四角形であり、四角錐の頂点の角度は90度である。 この場合においても、図3の結果と同様に、Dを変化させることで、位相状態が時計回りに変化している様子が確認できている。 ただし、図10のように、インピーダンスの調整量は変化している。 このことから、半導体部105の特性に応じて、アンテナ部の形状を適宜選択することで、アンテナ発振回路の位相条件を詳細に調整することが可能となる。 図6は、アンテナ高さHを変化させたときの周波数特性をプロットしたものである。 ここでも、アンテナ部102の配置位置Dは、1/4・λとしている。 解析周波数は、1.0THz乃至1.4THzである。 図6において、アンテナ部102の高さHが大きくなる程、アンテナの入力インピーダンスが高くなる傾向が分かる。 尚、この時のアンテナ共振周波数(虚数が0となる点)は、ほぼ1.2THzで一定である。 図4は、アンテナ部102の高さHに対する、アンテナ素子の入力インピーダンスの変化をプロットしたものである。 図4の様に、アンテナ部102の高さHの増加に対し、ほぼ線形に入力インピーダンスが高くなる様子が分かる。 例えば、このアンテナ素子をアンテナ発振回路として用いる場合、アンテナ部102の高さHによって、動作周波数を変化させずに、負荷抵抗を高くすることができることを示している。 図5は、第1導体部101の線幅wを変化させたときの、アンテナ素子の入力インピーダンスの変化をプロットしたものである。 ここでは、アンテナ部102の高さは1/2・λとしている。 解析周波数は、1.0THz乃至1.4THzである。 図5の様に、第1導体部101の線幅wの減少に対し、ほぼ指数関数的に入力インピーダンスが上昇している様子が分かる。 例えば、このアンテナ素子をアンテナ発振回路として用いる場合、第1導体部101の線幅wによっても、動作周波数を変化させずに、負荷抵抗を高くすることができることを示している。 半導体部105として光伝導膜を用いた場合、本実施形態のアンテナ素子は、外部からの光照射によって発生したキャリヤに起因する電磁波を外部に放射する動作を行う。 また、半導体部105として、電磁波に対して利得を有する機構を用いた場合、本実施形態のアンテナ素子は、発振が開始する条件を満たすための負荷抵抗として機能し、電磁波を外部に放射する動作を行う。 この負荷抵抗は、上記の方法により柔軟に設定することができる。 本実施形態のアンテナ素子は、アンテナ部が外部(共振部の第1導体部上)に支持される構成であるため、平面アンテナ構造に比べ、誘電体部104による損失を低減できる。 また、この誘電体部104は、使用する電磁波の波長(上記数値例ではλ=300μm)に対し、十分薄く(例えば、数μmであり、上記数値例では3μm)することができる。 そのため、不要な伝播モードが立ちにくい構造となり、誘電体部104による閉じ込め効果を低減することができる。 こうして、電磁波の取り出し効率(検出では取り込み効率)が向上する。 特に、本実施形態のアンテナ素子を発振素子として用いた場合、テラヘルツ波領域においても、上記の如く十分な負荷抵抗を維持できるため、発振条件を満たすことが比較的容易になる。 そのため、本実施形態の発振素子は、比較的安定的に発振することが可能となる。 次に、より具体的な実施例について、図面を参照して説明する。 尚、本発明のアンテナ素子は、これらの実施例に限定されるものではない。 上記課題を解決するための手段のところで述べた構成の範囲内で、各要素は種々の形状、材料、配置関係などで構成できる。 (実施例1) 本実施例では、第1導体部101として、金(Au)(厚さ0.5μm。以下、括弧内の数値は厚さを表す)/チタン(Ti)(0.03μm)を用いる。 線路長Lは150μm、線路幅wは15μmにする。 第2導体部103は、不図示の誘電体基板(本実施例では半絶縁性のインジウムリン(InP)基板)上に形成する。 第2導体部103としては、Au(0.5μm)/Ti(0.03μm)を用いる。 誘電体部104は、第2導体部103にBCBを3μm塗布する。 第1導体部101は、誘電体部104にプリントされる。 この様にして共振部を構成する。 本実施例では、半導体部105としてRTDを用いる。 半導体部105は、インジウムガリウムヒ素(InGaAs)/インジウムアルミニウムヒ素(InAlAs)ヘテロ接合からなる3重障壁量子井戸構造の活性層を有する。 これらの活性層は、分子線エピタキシャル法(MBE法)によって、不図示の誘電体基板にエピタキシャル成長することによって形成できる。 そして、シリコン(Si)を高濃度にドープしたn + InGaAsを、上記活性層の上下に積層し、コンタクト層とする。 このコンタクト層によって、半導体部105は第1導体部101と第2導体部103との導通を実現する。 本実施例の上記活性層構造は、第1導体部101から第2導体部103にかけて下記の通りとなっている。 また、本実施例では、半導体部105にバイアスを印加するためのバイアス回路(不図示)を第1導体部101と第2導体部103間に付加する。 バイアス回路は、アンテナ素子を伝播する電磁波への影響を最小するにするため、電磁界の節となる位置(電界が0となる位置)に接続することが好ましい。 アンテナ部102は、シリコン球にAuをコーティングしたものを用いる。 アンテナ部102の高さH、すなわちシリコン球の直径は150μmのものを用いる。 アンテナ部102は、第1導体部101上の任意の位置にAu-Au圧着によって接続する。 尚、接続方法は、これに限らず、既存のハンダ接続等のプロセス技術を用いることもできる。 アンテナ部102に用いたシリコン球の一般的な(入手可能な)径は、数10μm乃至数100μmである。 この形状に対応する波長域は、テラヘルツ波における1波長分程度或いはそれ以下に相当する。 このことから、本実施例におけるアンテナ素子は、好適には、テラヘルツ波領域において用いられる。 また、テラヘルツ波領域における、上記RTDのインピーダンスの実部は、およそ30Ω以上と見積もることができる。 従って、発振を開始するための条件を満たすため、アンテナ素子に必要な負荷抵抗は、少なくとも、この値以上必要である。 図4において、この条件を満たすアンテナ部102の高さHは、1/4・λ以上である。 以上のことから、このアンテナ素子をテラヘルツ波領域において用いる場合、好適には、アンテナ部102の高さは1/4・λからλであることが望ましい。 また、第1導体部101と誘電体部104の界面からアンテナ部102の最上部までの高さはλ以下であることが望ましい。 図3及び図6からも明らかなように、上記アンテナ素子は、アンテナ部102の配置位置と高さによって位相条件が変化する。 そのため、好適には、上記アンテナ素子は、発振を開始するための条件を満たすため、第1導体部101上のアンテナ部102の配置と高さによって、位相条件を調整し、発振条件を得る。 ただし、場合によっては、位相スタブなど、位相を調整する回路を別途設ける態様も可能である。 上述した様に、本実施例におけるアンテナ素子は、テラヘルツ波領域において、十分な負荷抵抗を維持することができる。 そのため、発振条件を満たすことが容易になり、発振動作が容易になる。 また、広帯域なアンテナ構造への適用において、パッチアンテナの様な共振型のアンテナに比較して、発振条件を満たすポイントが増え、発振動作の歩留まりが向上する。 勿論、実施形態のところで述べた効果も奏される。 (実施例2) 本実施例では、半導体部105として光伝導膜を用いる。 具体的には、低温成長(LT)させたガリウムヒ素(GaAs)薄膜を第2導体部103に移設して、上記アンテナ素子を構成する。 具体的には、GaAs基板に、犠牲層としてのアルミニウムヒ素(AlAs)(100nm)、LT-GaAs層(2μm)を、MBE法にて順次成長させる。 LT-GaAs層表面に電極を形成し、第2導体部103と電極面を、ハンダで融着する。 その後、GaAs基板を、過酸化水素とアンモニアの混合液でエッチングする。 このエッチングは、上記犠牲層でストップし、この犠牲層を濃塩酸で除去することで、第2導体部103上に、光伝導膜を形成する。 尚、ここでは、光伝導膜として、GaAs系について述べたが、これに限らない。 他の半導体として、InPやインジウムヒ素(InAs)を用いてもよい。 また、有機半導体で、光伝導性があるものを用いてもよい。 本実施例におけるアンテナ素子では、上記バイアス回路によって、半導体部105にバイアスを印加した状態で、チタンサファイア・フェムト秒レーザ等の外部からの光を半導体部105に照射する。 この時、外部からの光照射によって発生したキャリヤに起因する電磁波を、テラヘルツ波として外部に放射するものである。 また、本構成は、上記背景技術のところでも説明したように、テラヘルツ波の検出器としても適用できる。 従来の光伝導素子は、アンテナ構造に対して、両法線方向にテラヘルツ波を放射していた。 本実施例におけるアンテナ素子は、テラヘルツ波の指向性を第2導体部103によって、一方向に規定している。 そのため、従来の光伝導素子に比較して、電磁波の取り出し効率(検出では取り込み効率)が高い。 また、テラヘルツ波の放射方向を一方向に規定することにより、不要な放射を抑制し、例えば、アンテナ素子の集積化を容易にする。 (実施例3) 本実施例では、第1導体部101とアンテナ部102を機械的に接続する。 具体的には、図7の様に、保持部706によって、その開口部のところに球状のアンテナ部102の頂部を嵌め込んだ状態で、アンテナ部102を覆う。 こうして、保持部706と誘電体部104を機械的に固定することによって、アンテナ部102を第1導体部101上に固定する。 保持部706としては、テラヘルツ波に対し透明(損失が少ない)である部材を用いることが望ましい。 例えば、ポリイミド系、ポリオレフィン系の様な樹脂材料や、高抵抗シリコンの様な半導体材料を用いることができる。 機械的な固定方法としては、例えば、図7の様に、共振部側に孔を開け、保持部706に設けたピンをその孔に挿入する態様がある。 ただし、固定方法はこれに限らず、共振部側にピンを設け、保持部706に設けた孔によって固定する態様も考えられる。 要は、アンテナ部102を、保持部706と共振部によって挟み込み、機械的に固定できる形態であればよい。 また、図7では、共振部を構成する第1導体部101とアンテナ部102は、接触した形で固定されているが、これに限らない。 例えば、アンテナ部102の上部及び下部を保持部706で挟み込み、これを一つのユニットとする。 そして、このユニットを共振部に対し任意の高さ方向の位置に固定することで、第1導体部101に対して、或る間隙を隔ててアンテナ部102を配置することもできる。 本実施例におけるアンテナ素子は、第1導体部101に対してアンテナ部102を機械的に固定、配置している。 そのため、第1導体部101とアンテナ部102の接続状態が、プロセス技術の歩留まりに依らなくなる。 その結果、接続部分における寄生成分を一定化でき、アンテナ素子としての能力の歩留まりが向上するという効果がある。 また、外部の保持機構によって、或る間隙でもってアンテナ部102を第1導体部101に対して固定することができる。 この間隙は、容量成分として用いることができる。 これにより、例えば、このアンテナ素子をアンテナ発振器として用いる場合、位相条件を整合させるためのパラメータが増える。 そのため、発振の歩留まりが向上するという効果がある。 (実施例4) 本実施例では、アンテナ部102を機械的に保持するための保持部706の位置を変化させる可動部を有している。 例えば、図8の様に、共振部側に溝形状の可動部807を設け、この溝形状部に沿って保持部706のピンを第1導体部101の長手方向(電磁波の伝播方向)に移動可能とする。 可動部807の構造はこれに限らず、例えば、ピエゾアクチュエータの様な、外部の制御信号によって位置が変化するアクチュエータを可動部内に作り込む態様も考えられる。 すなわち、例えば、保持部706のピンを挟んで溝形状可動部内の両側にピエゾアクチュエータを設け、制御信号で両側のピエゾアクチュエータの厚みを変化させて保持部706のピンを第1導体部101の長手方向に移動させる構造が可能である。 また、実施例3と同じく、溝形状の可動部807が保持部706側にある態様であってもよい。 この様な構成を有することで、アンテナ素子を作製後であっても、アンテナ部102の位置が可変となる。 例えば、このアンテナ素子をアンテナ発振器として用いる場合、アンテナ素子の出力をモニタし、発振条件が成立する箇所に、再度調整することが可能となる。 また、このアンテナ素子を光伝導素子として用いる場合、最も取り出し効率が良くなる条件に再度調整することができる。 そのため、アンテナ素子としての歩留まりが上がり、作製コストが低下するという効果がある。 101 第1導体部 |
||||||